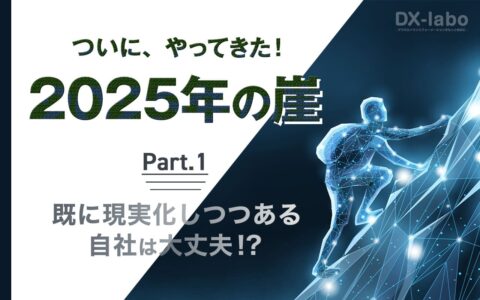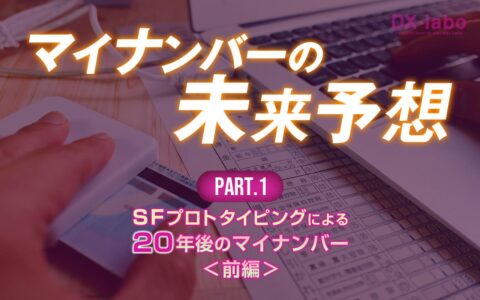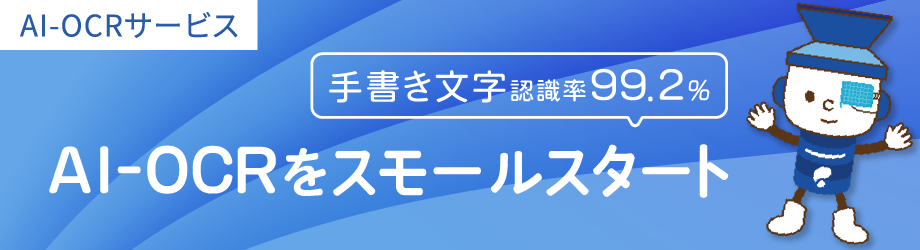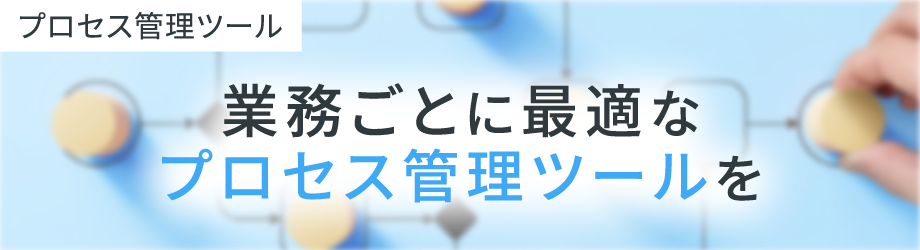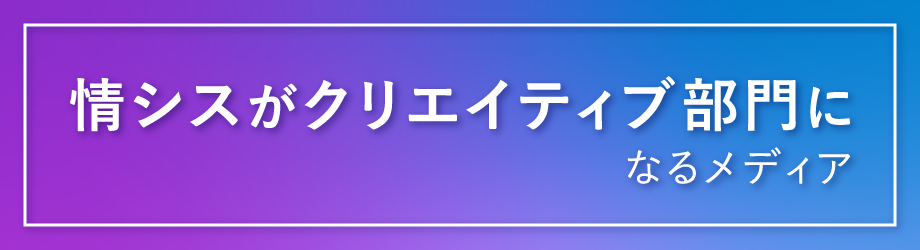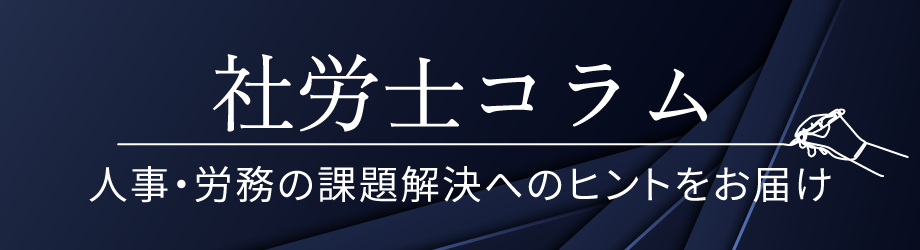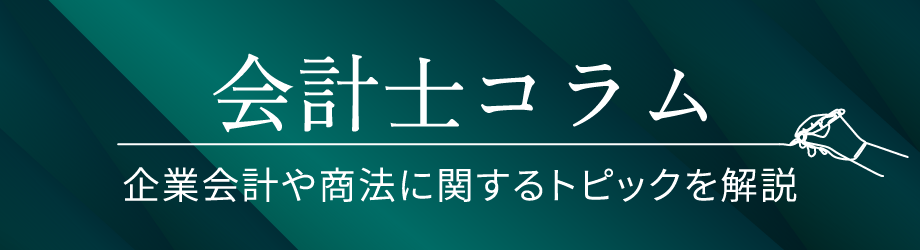「2025年の崖」から転落しないために必要な3つの取り組み
ついに「2025年の崖」がやってきた!<後半>
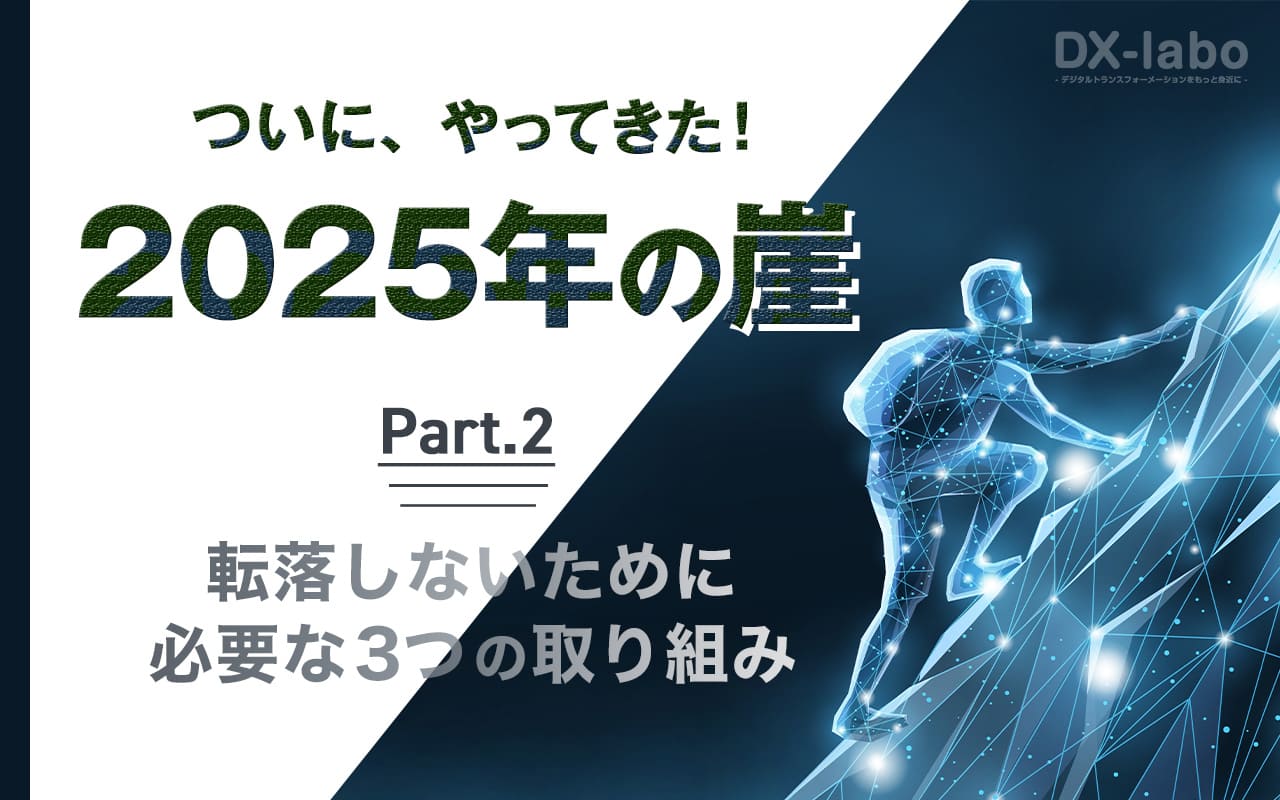
多くのメディアでは、企業が「2025年の崖」に転落しないために必要な対策として、レガシー化(複雑化・老朽化・ブラックボックス化)した基幹システムを刷新し、DXを推進することが挙げられています。確かにそれは間違いではありません。しかし、システムの刷新そのものが目的化してしまうと、本来目指すべき成果からはかけ離れてしまう可能性があります。
経済産業省が『DXレポート2(中間取りまとめ)』(2020年12月公表)で指摘しているように、DXの本質は「レガシー企業文化からの脱却」にあります。技術的な課題の解決も重要ですが、その前に、レガシー化を引き起こした原因となる企業文化や慣習を見直し、変革することが欠かせません。今回は、そのために習慣化し、徹底すべき3つの取り組みについて解説します。
(1)「見える化」から始める
ここで言う「見える化」とは、企業が自社システムの状況を把握できるようにするための取り組みを指します。ビジネスにおいて、「To-Be(あるべき姿)」を実現するためには「As-Is(現状)」の明確化が不可欠。レガシーシステムの刷新においても、情報資産の現状を把握できていなければ、どこに課題があるのか、どのように構築すべきかを適切に判断することはできません。
ただし、現状の見える化だけでは十分とは言えません。洗い出したシステムの無駄や非効率、リスクに対して実施した施策がどのような効果をもたらしたのか、また、それに伴う投資が適切だったのかについても可視化し、明確に評価・検証するプロセスも重要です。
もう1つの重要なポイントは、自社で「何を、どのように見える化するのか」を明確にし、簡潔な指標と診断の仕組みを構築することです。このアプローチによって、ベンダーやコンサルティング企業に一任するよりも中立的な診断が可能になり、経営トップにもシステム刷新を経営課題として認識してもらいやすくなります。また、ビジネス部門の協力を得ることで、ビジネス視点からの課題発見や改善にもつながります。
(2)ベンダーとの関係を見直す
日本では、自社お抱えのSIベンダーに全面的に依存している企業が少なくありません。しかし、経済産業省の『DXレポート2.1』(2021年8月公表)では、こうしたユーザー企業とベンダー企業の関係性について、「両者がデジタル時代において必要な能力を獲得できず、デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な『低位安定』の関係に固定されてしまっている」と指摘されています。
この依存関係がもたらす具体的な問題としては、「自社のIT対応能力が向上しない」、「活用可能なツールやシステムが制限される」、「経営の迅速性や柔軟性が低下する」といった点が挙げられます。これらはいずれもDX推進の大きな障壁となるものであることは言うまでもありません。もちろん、一方ではメリットもあり、一概に否定できるものではありませんが、結果として「デジタル競争で勝ち抜けない」という事態に陥ってしまうのであれば本末転倒です。
例えばアメリカ企業では、CIO(最高情報責任者)やIT部門が、誰も使っていないベンダーを発掘してくることで評価を得るケースが珍しくないそうです。今後は日本企業でも、従来の枠組みにとらわれない革新的な提案をおこなうベンダー企業にも広く目を向け、その技術の導入・活用に挑戦しようとする社員を評価する文化や仕組みを整えることが求められるのではないでしょうか。
(3)IT部門をデジタル戦略的部門へ変革する「開発への意識」
DX推進企業のIT部門に求められるマインドの1つが「開発への意識」です。これは実際に開発業務に携わっているか否かは関係がありません。具体的には、自部門を社内に向けてサービスやソリューションを提供するサービス提供者として位置付け、常にシステムのアップデートを欠かさない姿勢を指します。
この意識が必要な理由は、ビジネスを取り巻くIT・デジタル環境の変化のスピードが加速しているためです。こうした状況では、常にアップデートしていく意識がなければ、構築・導入したシステムはすぐに陳腐化してしまい、それに対して「運用でカバーする」という場当たり的な対策に陥るリスクがあります。こうした事態を防ぐためには、ユーザー視点を取り入れつつ、システムを継続的に改善し進化させることが不可欠です。
具体的な改善の方法としては、自社の開発者またはSIベンダーと連携し、短いスパンでITシステムの改良を繰り返すことが挙げられます。このように開発と運用が緊密に連携する組織体制は、レガシーシステム刷新のプロジェクトにおいても効果的です。また、そのプロセスで得られるナレッジをサービスとして外部に提供し、DX支援などの新たな事業を生み出している企業も少なくありません。このように開発への意識は、IT部門が単なる支援部門にとどまらず、自社の成長に直接貢献する組織へと変化する可能性を秘めているのです。
なお、DX時代のIT部門に求められる知識やノウハウについては『SmartStage』というメディアでも紹介しています。興味のある方は是非一度ご覧ください。