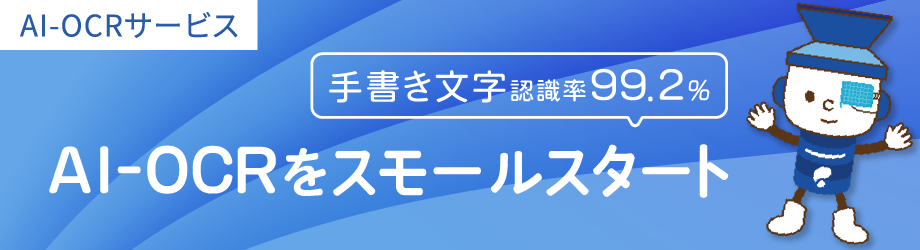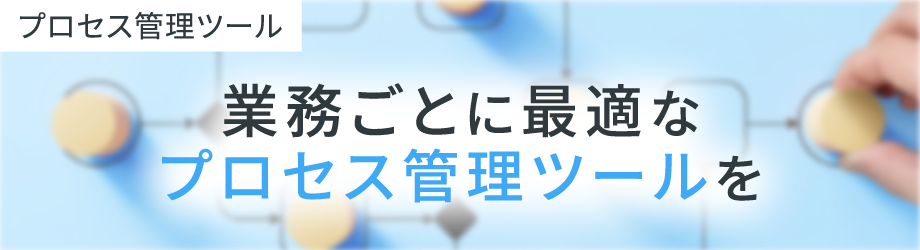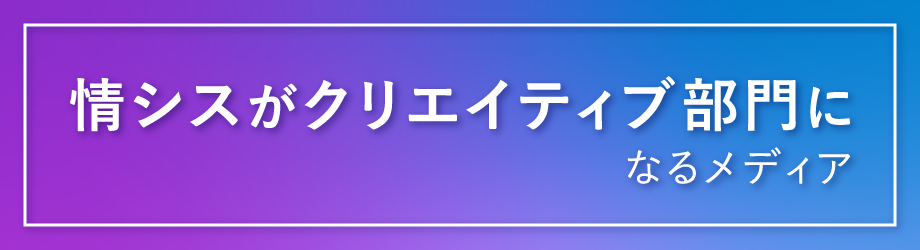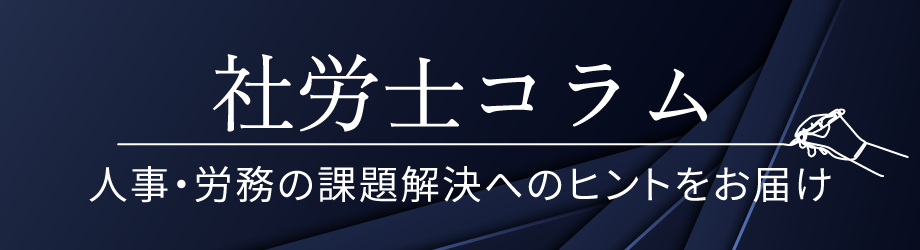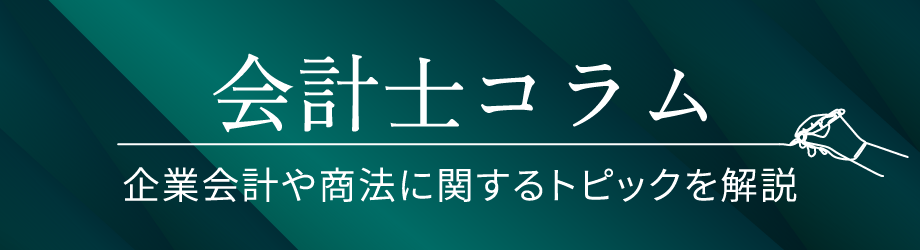<Flutter攻略への道・開発基盤の構築>第8回 Flutter基盤構築の全貌とその学び ― 開発現場からのリアルな学び
デベロッパーズ・インサイト「最新技術の実践レポート」

開発を通しての総括
導入部でお伝えしたとおり、私たちの部署ではテレワーク主体の働き方への移行に伴い、社員同士のコミュニケーション不足が課題となっていました。この課題への対応策として、部内向けポータルアプリをスマートフォン向けに開発することを決定し、同時に将来のアプリ開発にも活用できる共通基盤の構築に取り組んできました。
これまでの連載では、基盤の構想や標準機能、部内ポータルの機能、開発構成などについてご紹介してきました。最終回となる今回は、開発を通して得た気づきや学び、そして総括をお伝えしたいと思います。
当初の想定と、実際の開発経験から見えてきたこと
プロジェクト開始当初、私はWebアプリケーションの開発経験から、「基盤構築とは、共通処理を一から作り上げていくもの」と漠然と考えていました。ユーザー認証・管理、Push通知、エラーハンドリング、オフライン対応など、必要な機能を洗い出し、アプリ全体に影響する共通処理の整理から取りかかったのです。
しかし、Flutterでの開発を進める中で、私の認識は大きく変わりました。Flutterには非常に豊富なライブラリやパッケージのエコシステムがあり、多くの共通処理はそれらを活用することで解決できます。また、Flutterフレームワーク自体も多くの基盤機能を備えており、独自に実装する必要性は、当初の想定よりもはるかに少ないことに気づかされました。
今振り返ると、連載初期に書いていた「一から作る」という発想自体が、的外れだったかもしれません。
エコシステムの豊かさと、選定の重要性
第7回でもご紹介したように、実際の開発では「アーキテクチャ」と「パッケージの選定」に最も時間をかけました。MVVMパターンの採用、Riverpod 2.x+Flutter Hooksによる状態管理、Freezedによる型安全なデータ定義、go_routerによる画面遷移管理など、慎重に検討を重ねた結果、現在の構成にたどり着いています。
振り返ると、この「選定のプロセス」こそが、基盤構築における最も重要な工程だったと感じています。適切なライブラリや設計を選ぶことで、開発者が特別意識しなくても、共通処理や設計の一貫性が自然と保たれる開発環境が整うのです。
例えばRiverpodの導入により状態管理の一貫性が担保され、Freezedを使えばデータクラス周りのバグを未然に防ぐことができます。

基盤構築の真の意味とは
この経験を通して私が得た学びは、「Flutterにおける基盤構築とは、ゼロから作ることではない」ということです。適切なライブラリとアーキテクチャパターンを選び、それらを統合・最適化することで、一貫性ある開発基盤を整備する――それこそが、Flutter開発における基盤構築の本質だと感じました。
もちろん、アプリ固有のビジネスロジックやエラーハンドリングの共通化は必要ですが、独自実装が必要な領域は当初想定よりもはるかに少なかったというのが正直な実感です。
クライアントのニーズに柔軟かつ迅速に対応するには、堅牢な基盤の上に開発を進める必要があります。そして、その基盤は、ゼロからではなくFlutterのエコシステムを最大限に活用することで構築できるのです。
今後の展望
このプロジェクトで得た知見は、今後のさまざまなアプリ開発にも活かせると考えています。第6回で紹介したとおり、社内業務の効率化ツールや顧客向けプロトタイプ、プラグイン式テンプレートなど、用途は多岐にわたります。
また、今回構築した基盤を活用することで、クライアントの要望に対して迅速にプロトタイプを提示し、スムーズに本開発へと移行できる体制が整いました。これは、提案力の強化や受注率の向上にもつながると期待しています。
今後も社内ポータルアプリの開発を継続しながら基盤のブラッシュアップを図り、そこで得られた知見を社内で共有することで、当社全体のモバイルアプリ開発力を高めていきたいと考えています。
このコラムが、皆さまのプロジェクトにも何らかの形でお役に立てれば幸いです。