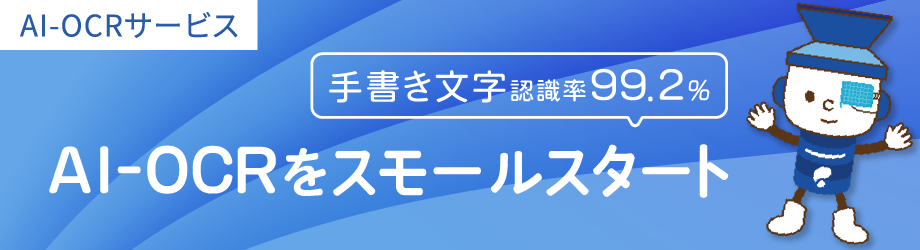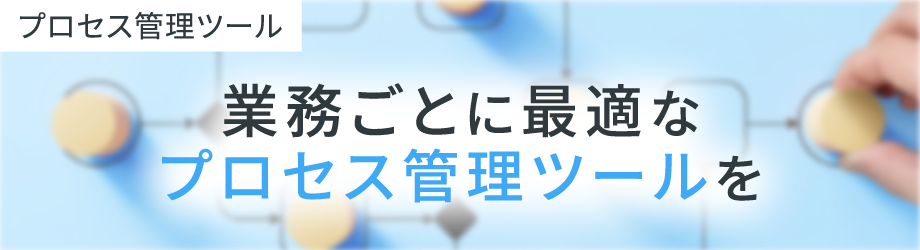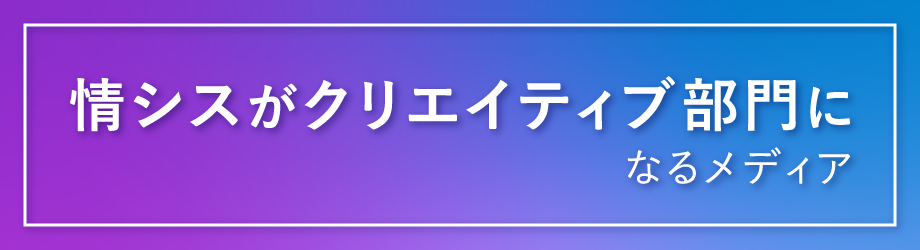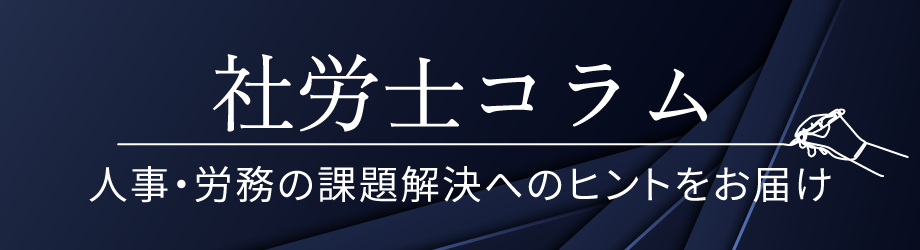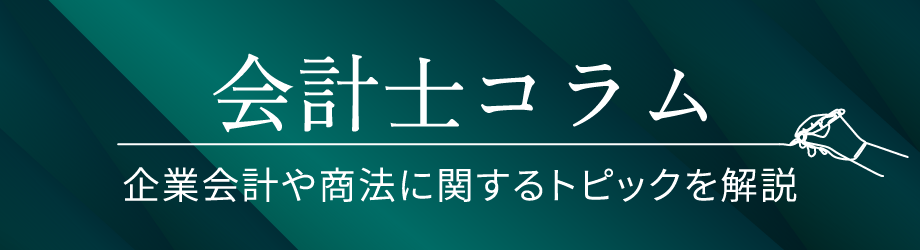AIブラウザ時代の幕開けと覇権争い
Google I/O 2025で始まるAI戦争の新章

前回はGPT一強の時代は終わるのか、Google I/O 2025が描く未来、アプリに統合されるAI・AIネイティブブラウザについて解説しました。今回は、Comet、Genspark、DiaといったAIブラウザの台頭などについて詳しく見ていきましょう。
AIブラウザの台頭:Comet・Genspark・Dia
従来、AIは「必要なときに呼び出して使う存在」でした。しかし、日常業務や調査、学習、創作などをAIが伴走するようになった現在、より密接で軽快なユーザー体験を追求する動きが広がっています。
その象徴が、AIネイティブブラウザと呼ばれる新たなジャンルのツールです。ここでは代表的な3つの製品を紹介します。
Comet:知識を“育てる”AIブラウザ
Cometは、ブラウザ上で得た情報やAIとの対話を自動で整理・蓄積し、「パーソナルナレッジベース(自分専用の知識ベース)」として再利用できるのが特徴です。ユーザーは「このやり取り覚えておいて」と明示しなくても、文脈ごとに情報を保存し、次回のタスクや調査に活かせる設計になっています。
研究職やコンサルタント、ライターといった「思考を蓄積する」タイプの仕事との相性が良く、情報整理や調査メモの自動生成などに力を発揮します。
Genspark:RAG検索とAPI連携に強い軽量AI
日本語対応が優秀で、軽快なUIが特徴のGensparkは、生成AIをもっともシンプルに体感できるブラウザのひとつです。特徴的なのは、「RAG(検索+生成)による正確な情報回答と、外部APIとの連携」です。
たとえば「このドキュメントを読み込んで要約して」「このPDFから仕様を抽出して」といったタスクに対し、Gensparkは高速かつ的確に対応。さらにNotionやSlackなどとの連携も容易で、「作業のハブ」としての実用性が評価されています。
Dia:SNSやデザインツールと融合した創作支援型AI
Diaは、AIを活用したビジュアル制作、SNS投稿作成、キャッチコピー提案など、クリエイター業務に特化したAIブラウザです。Chat UIを前提としながらも、画像生成、ショート動画作成、トレンドワード提案などのツールが内蔵されており、直感的に「コンテンツを作るAIアシスタント」として活躍します。
また、InstagramやTikTokなどへの自動投稿支援など、SNS運用者にとって実用的な機能が盛り込まれているのも特徴です。
これら3つのAIブラウザに共通しているのは、単なる「AIとの会話」ではなく、“一緒に作業しながら最適な情報を渡してくれる存在”としてのAI像です。「使うAI」から「共に過ごすAI」へのシフトが、UX(ユーザー体験)の領域で静かに進行しているのです。
OpenAIの立ち遅れと今後の布陣
AI UX の最前線で意外と出遅れているのが OpenAI です。GPT‑4o は音声・画像・動画対応の高性能モデルであり、API や GPT Store、デスクトップアプリでの機能拡張も進んでいます。
さらに、2025年6月に登場したGPT‑5 は、論理的推論力、長期文脈の保持、個人プロファイル適応力を大きく強化しており、“業務向けアシスタント”としての完成度を高めています。
とはいえ、「Web を見ながら自然に補助してくれる常駐型 AI」という体験では、Google や AI ブラウザ勢に UX 面でやや劣る印象です。
そこで OpenAI が仕掛けたのが Apple との連携です。2025 年に発表された「Apple Intelligence」により、Siri、メール、メモ、Safari 検索に GPT‑4o が統合され、Apple デバイスで自然なアシスト体験を実現し始めました。OS レベルでの UX 強化という意味では重要な一歩ですが、まだ初期段階であり、ユーザーへの浸透や習慣化にはこれからともいえます。
次の主戦場は「ブラウザ」か「OS」か?
AIの主戦場は、かつての「LLM性能競争」から、今や「どこでどのように使えるか」というUX体験競争へと移りつつあります。
各社の戦略を簡単に整理すると以下のようになります。
プレイヤー/主戦略
Google/Gmail・Docsなどのアプリ主導型統合AI
Microsoft/Copilotを中心にしたOffice統合戦略
OpenAI/高性能LLM+API市場主導
Apple/iPhone中心のデバイス内AI体験(Apple Intelligence)
新興勢力/軽量・高速・パーソナル最適化ブラウザ
特に「ブラウザ」は、ユーザーのあらゆる作業の入口であり、「常駐AI」にとっての重要な戦場です。
一方で、Googleは「OSレベルでのAI統合」においてAndroidやChromeという武器を活かし、全方位的なアプローチを採用しています。
今後は、この「OSに統合されるAI」と「ブラウザに寄り添うAI」のせめぎ合いが、焦点となるとも考えられます。
まとめ
今後のAI市場では、単なる「賢さ」や「正確さ」だけではなく、どれだけ自然に、日常に、気が利くかが勝負の分かれ目になります。
さらに最近では、「AIアシスタント」から一歩進んだ概念として、「AIエージェント」も注目されつつあります。アシスタントが「ユーザーの指示に応える存在」であるのに対し、エージェントは「自律的にタスクを判断・実行する存在」として、より主体的にユーザーを支援するAIです。
まだ実用段階ではエージェント型の導入は限られますが、近い将来には「AIエージェント」が一般化する可能性もあり、UX設計の在り方にも大きな影響を与えるでしょう。
今後のAIアシスタントは、「何をできるか」よりも「どこでどんなふうに使われるか」という、体験の質と場面適応力が重視される時代に移行しています。
生成AI戦争は、ようやく次のフェーズである『日常に溶け込むAI体験』へと突入したともいえます。