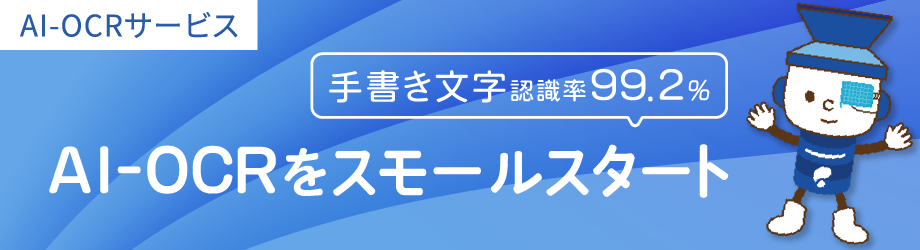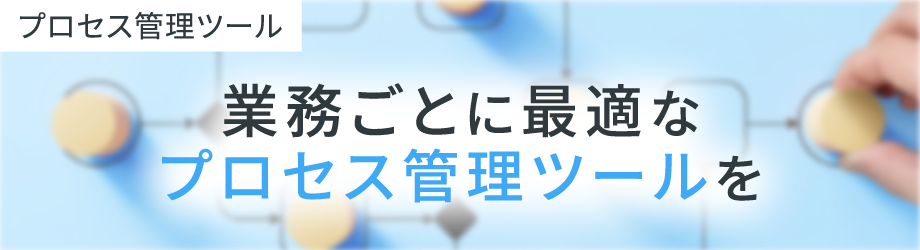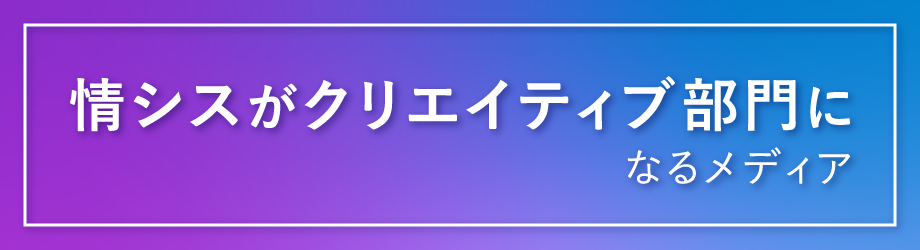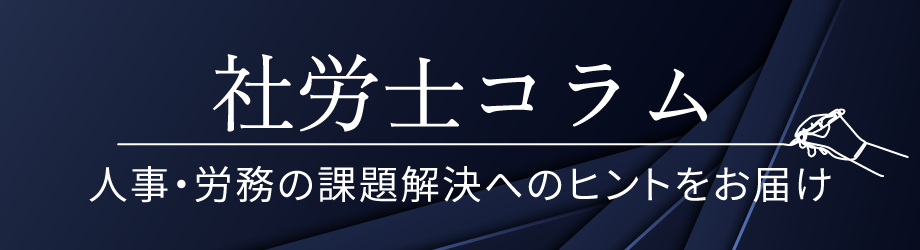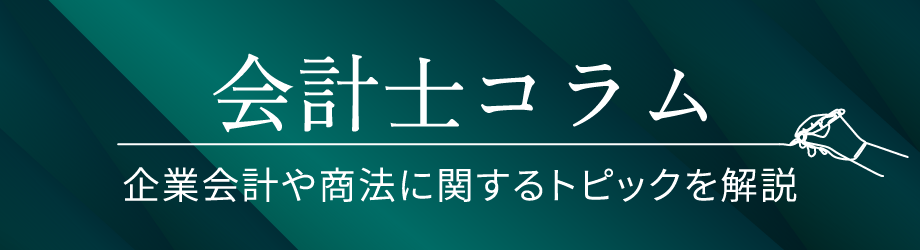DX推進企業も実践! アナログ+デジタルの驚きの効果とは?
デジタル時代だからこそ効く!アナログ・オフライン活用施策
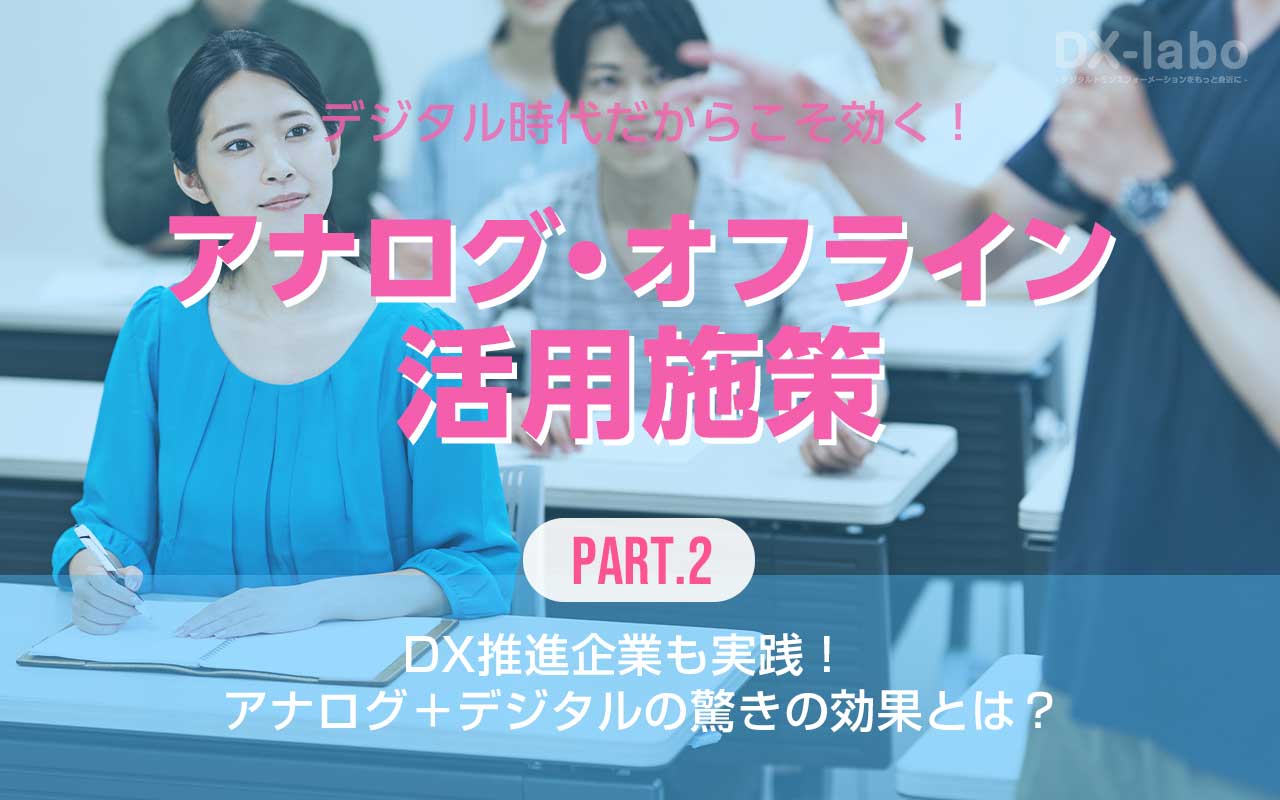
前半記事で述べたように、アナログ・オフラインには、ビジネスにおいてデジタルでは代替できない強みがあります。今回も引き続き、DX推進企業も実践するアナログ・オフライン活用施策を実際の事例とともに紹介します。
デジタルを上回る「紙のダイレクトメール」の強み
紙のダイレクトメール(DM)は、アナログ施策の代表格として長らく活用されてきました。そのため、現在では「オワコン(既に役割を終えた手法オワコン)」と見なされることも少なくありません。確かに、営業メールやメルマガ、SNS広告といったデジタル施策と比べると、制作や発送に手間とコストがかかるのは事実です。
しかし、物理的な「モノ」として届けられる紙DMには、そうした弱点を補って余りある強みがあります。
・読まれる割合が高い
営業メールやメルマガは日々大量に届くため、メールボックスで埋もれてしまいがちですが、紙DMは手に取ってもらえる確率が高く、結果として閲読率も大幅に上回ります。一般社団法人 日本ダイレクトメール協会が2025年3月に発表した『DMメディア実態調査2024』によると、自分宛てのDMの閲読率は74%に達しています。
・行動喚起率が高い
ここで言う“行動”とは、「DMの内容をネットで調べる」「商品やサービスを購入・利用する」「資料請求や会員登録をおこなう」など、企業にとって価値のあるアクションを指します。『DMメディア実態調査2024』では、本人宛DMの閲読後に何らかの行動を起こした割合は21%、つまり5人に1人が行動に移しているという結果でした。
DX推進企業の紙DM活用事例
紙DMは、デザインや形状を工夫することで、さらなる付加価値を生み出すことも可能です。例えば、保存率を高めたりパーソナルなつながりを深めたりするために、手書きのDMや、飛び出す絵本のように開封すると立体型に変形するDMを送付している企業もあります。
また、興味深いのは、旧来型の企業だけでなく、ソフトバンク株式会社やグーグル・クラウド・ジャパン合同会社といった、先進的なDX推進企業やIT系企業も積極的に紙DMを活用していることです。
例えば、経済産業省の定める「DX認定事業者」に認定されている三井住友カード株式会社では、効果向上のために、デジタル技術と紙DMを組み合わせた施策を展開しています。法人向けDMの送付先を選定する際に、既存導入企業の属性や利用傾向をAIで分析し、成約・利用見込みの高い企業を抽出。実際にDMを発送したところ、従来の選定条件と比べ、4.5倍ものリード(見込み客)創出に成功したということです。
オフライン+オンラインで相乗効果を生みだす「OMO」
紙DMの事例で見たように、アナログ・オフラインの強みは単独で活用するだけでなく、デジタルと組み合わせることでさらに大きな効果を発揮します。その代表的な手法が「OMO(Online Merges with Offline)」です。
OMOは、オンライン(ECサイト・アプリなど)とオフライン(店舗・コールセンターなど)の顧客データを統合し、あらゆる接点でシームレスな購買体験を提供するマーケティング手法です。スマートフォンの普及などにより、消費者の購買行動がデジタル中心に移行したことを背景に、近年注目が高まっています。
身近な例としては、ファーストフード店のモバイルオーダーが挙げられます。ユーザーがスマートフォンやタブレットで事前に注文・決済を済ませ、レジの行列に並ぶことなく店頭または店内席で商品を受け取れる仕組みです。
OMOを導入することで期待できる主なメリットは次の2つです。
・機会損失リスクの低減
ユーザーの購買意欲が高まったタイミングでスムーズに購入できる環境を提供することで、機会損失のリスクを抑えることができます。
・顧客体験(UX)の向上
統合データをもとに顧客一人ひとりの行動履歴や興味・関心に応じたパーソナライズなアプローチが可能です。結果として、LTV(顧客生涯価値)の向上も期待できます。
DX推進企業のOMO活用事例
DX推進企業としても知られる大手老舗百貨店の高島屋は、OMOを活用して新たな価値提供に取り組んでいます。新宿高島屋と京都高島屋S.C.では、ショールーミングストア『Meetz STORE(ミーツストア)』を活用したOMOを展開。ショールーミングストアとは商品の販売ではなく、「体験・確認」に特化した店舗のことです。
『Meetz STORE』では、主に国内外のD2C(Direct to Consumer:自社ECサイトを通じて直接消費者に販売するビジネスモデル)ブランドによる食品・化粧品・衣料品・雑貨などをセレクト。店内にディスプレイされているのはサンプル品のみで、来店客は気に入った商品を『Meetz STORE』のECサイトで購入し、後日自宅などへ配送してもらう仕組みとなっています。
このように、ECだけでなくリアル店舗も活用することは、来店客・出展者双方に大きなメリットをもたらします。
・来店客のメリット
通常はオンラインでしか購入できない商品を、実際に手に取って試してから注文することができます。ショップではワークショップなどのイベントが開催されており、より深く商品を体験することも可能です。
・出展者のメリット
オンライン以外の顧客接点を創出できるほか、専属の販売員による接客を通じて、オンラインでは表現しづらい商品・ブランドのストーリーや想いを対面で伝えられます。同様に、顧客の生の声や購買意欲・動機などの定性情報を取得できる点も大きなメリットです。
参照:髙島屋グループがショールーミングストア事業を開始。(株式会社髙島屋)
参照:ショールーム型店舗「Meetz STORE」が京都にオープン!(TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD.)
ポイントは「目的に応じた適材適所」
今回はアナログ・オフラインの有効性に焦点を当てましたが、だからといって極端にアナログ施策に偏るのは、前半記事で触れた「デジタル至上主義」と同じく非現実的です。
現代のビジネスにおいてまず前提とすべきは、やはり効率性や拡張性、検索性、再現性などに優れたデジタル活用です。以前 『企業にとってペーパーレス化が重要な理由』という記事でも述べたように、文書や帳票の電子化・電子保存が不可欠な取り組みであることは変わりません。
そのうえで重要なのが、目的に応じた適材適所の視点です。紙DMとOMO(Online Merges with Offline)の事例が示すように、デジタルとアナログ、それぞれの特性を正しく理解し、目的に応じて使い分ける、あるいは組み合わせること。それこそが、手段の目的化に陥ることなく、両者の強みを最大限に引き出すための最も合理的なアプローチと言えるでしょう。