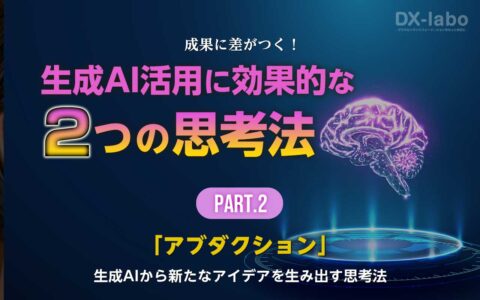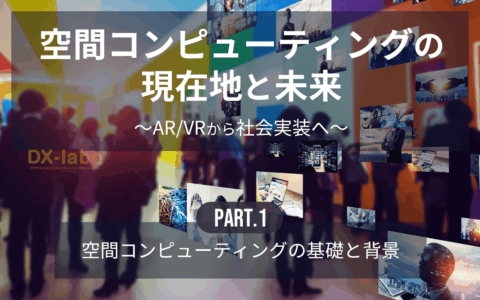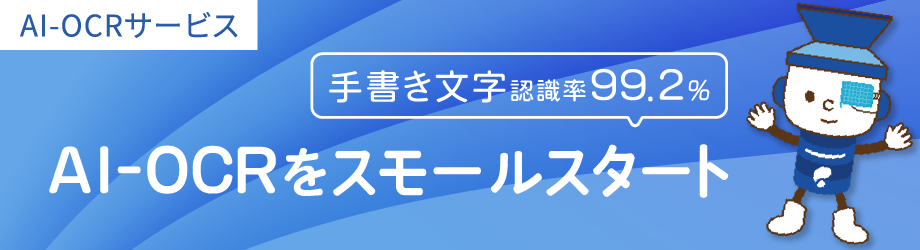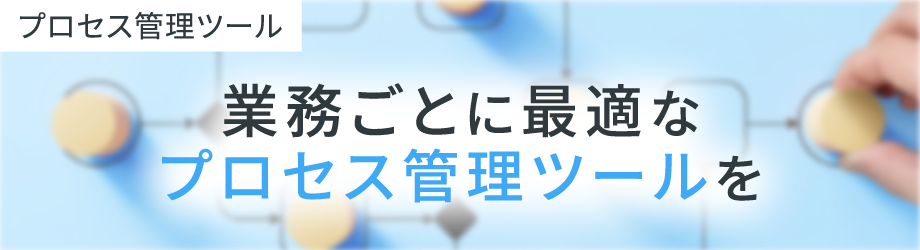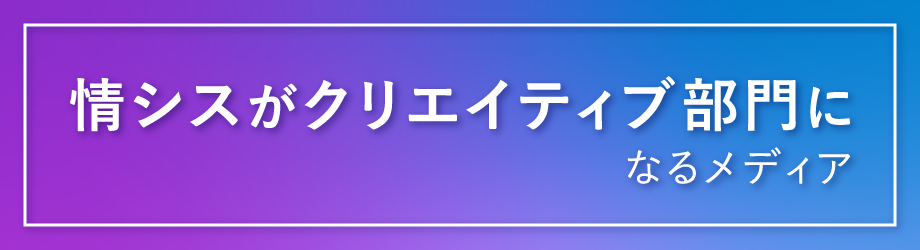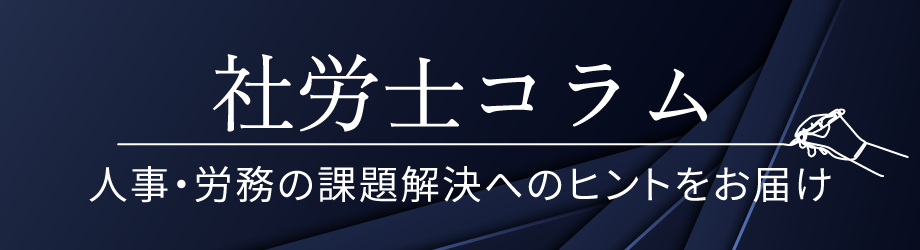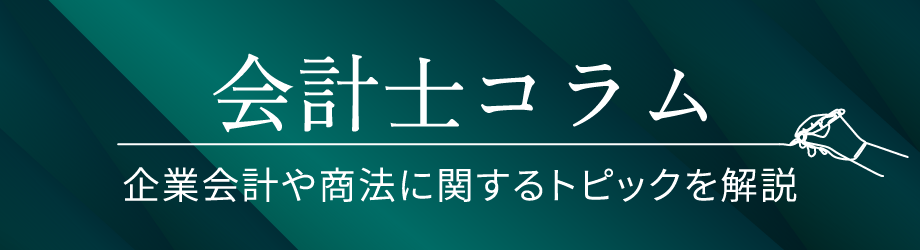生成AIに振り回されないための思考法「クリティカルシンキング」
成果に差がつく! 生成AI活用に効果的な2つの思考法
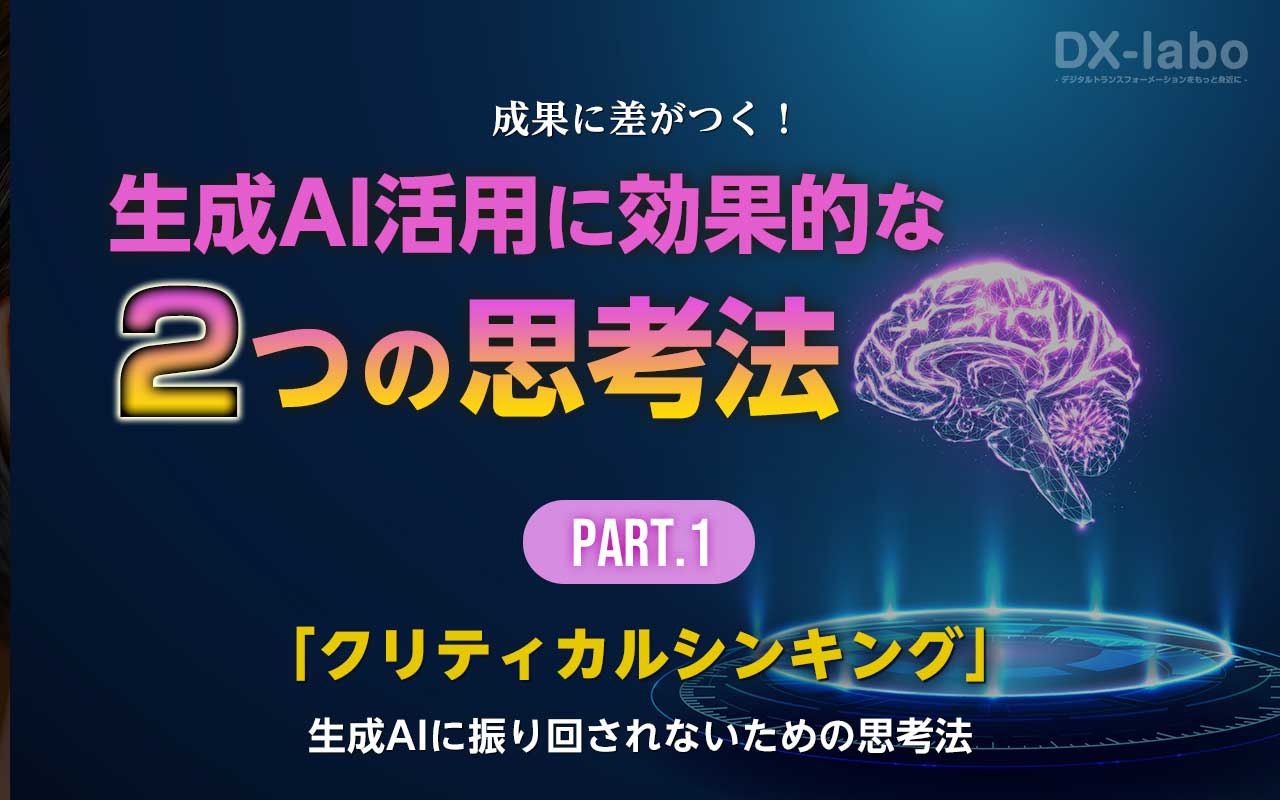
この『DX-labo』でも繰り返し取り上げてきたように、近年の生成AIの進化は目覚ましく、ビジネスでも既にさまざまな領域で活用が進んでいます。一方で、登場当初から指摘されてきたハルシネーション(事実と異なる、または現実には存在しない情報をもっともらしく生成する現象)などの課題は依然として解決されていません。
にもかかわらず、ビジネスの現場では、いまだに生成AIを「正解を教えてくれるツール」と過信し、出力された文章やアイデアをそのまま採用するケースも少なくないのが現状です。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が2025年6月に公表した『DX動向2025』でも、「誤った回答を信じて業務に利用してしまう」といった課題を抱えている企業の割合は、アメリカ・ドイツと比べて日本が突出して高い(※)と報告されています。
※出典:DX動向2025(p.41)|独立行政法人 情報処理推進機構
このような状況が続けば、企業やビジネスパーソンは「生成AIを使いこなして成果を生み出す層」と「使いこなしていると思い込んでいるだけで、実際は生成AIに振り回されている層」に二極化していく可能性すらあります。
既にハルシネーションを抑制する技術は登場していますが、現時点でそのリスクをゼロにすることは不可能です。だからこそ今必要なのはユーザー側のスキル、とりわけ生成AIへの依存によって低下が懸念されている“思考力”です。そこで今回は、生成AI時代に効果的と言われている2つの思考法を紹介します。
クリティカルシンキングの正しい意味
一つ目は「クリティカルシンキング(critical thinking)」です。日本語では「批判的思考」と訳されることが多いため、何かを非難したり否定したりするための思考法とネガティブに捉えられがちですが、それは本来の意味とは異なります。
もともと「critical」の語源であるギリシャ語の「kritiko」は、「見分ける・判断する」を意味する言葉であり、クリティカルシンキングは本来、「感情や主観に流されず、情報や根拠を多角的な視点から吟味・分析し、論理的でより妥当性の高い結論を導き出すための思考法」なのです。
こうした勘違いを避けるためか、クリティカルシンキングに「吟味思考」という訳語を当てているケースもあります。なお、この吟味の対象に「思考者自身の先入観やバイアス(思い込み)」が含まれている点もクリティカルシンキングの特徴のひとつです。
クリティカルシンキングの基礎力を養う“習慣”
生成AI時代にクリティカルシンキングを身に付けるメリットは、生成AIの出力を鵜呑みにせず、その正確性や公平性、利用可否を正しく評価・判断できるようになることです。また、前例や経験則が通用しない状況での意思決定の精度を高めることもできるため、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる時代において、ますます重要性が高まっています。
欧米の大学やビジネススクールではクリティカルシンキングは基礎教養として位置付けられており、本格的に習得するには研修や書籍による学習が不可欠です。ただし、一般のビジネスパーソンでも、日々の習慣を通じて基礎力を養うことは十分可能です。
とりわけ効果的なのが「前提を疑う」習慣です。例えば企画立案や問題解決に取り組む際に、無意識に前提としがちな自社の慣習や過去の成功体験、業界の常識などを、「本当に必要か?」「他の可能性はないか?」と問い直してみるといった取り組みが挙げられます。
他にも、会議で自分や他者の発言を「客観的な事実」と「個人的な意見」に分けて整理する、自分の立てた仮説に自分で反証を試みる、といった習慣も有効です。こうした積み重ねが、生成AIが出力する「もっともらしいウソ」に振り回されることなく、冷静に吟味・検証する力につながります。
次回の後半記事では、生成AIの出力から新たなアイデアを生み出すための思考法「アブダクション」について解説します。