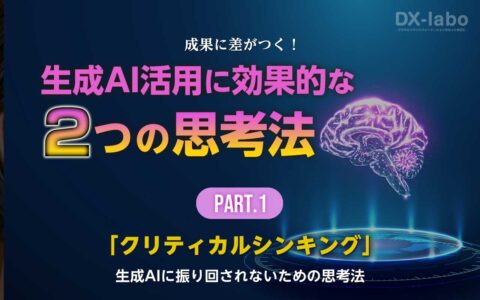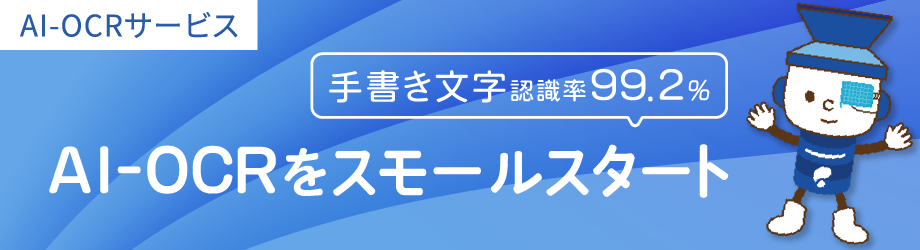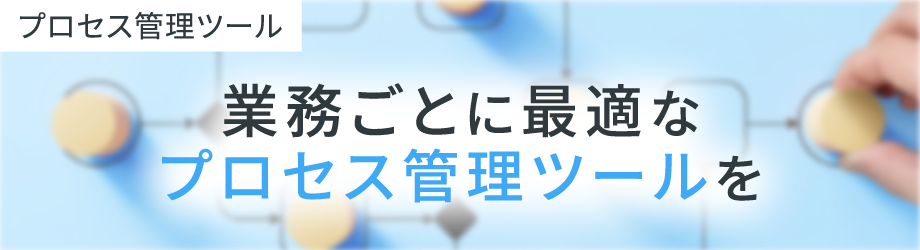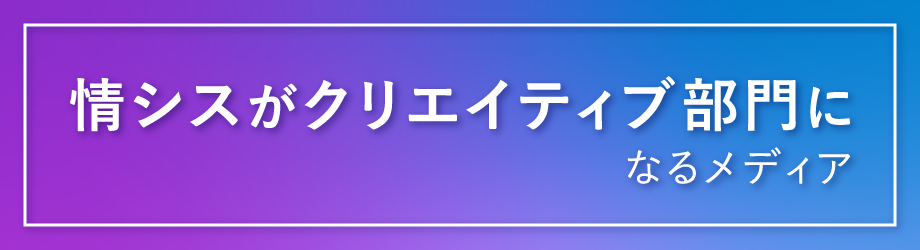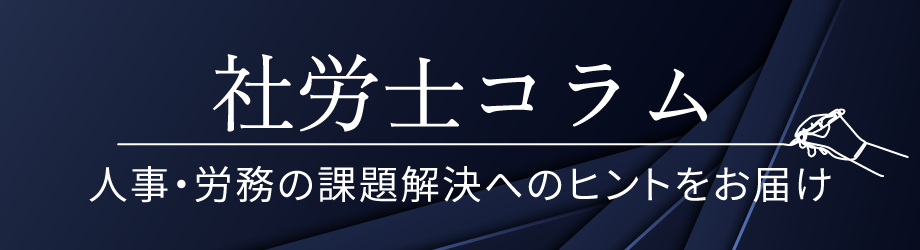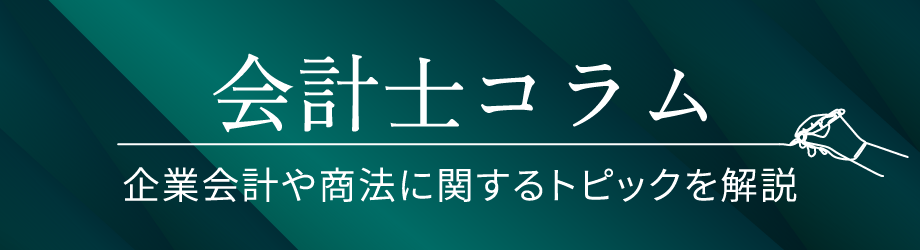生成AIから新たなアイデアを生み出す思考法「アブダクション」
成果に差がつく! 生成AI活用に効果的な2つの思考法
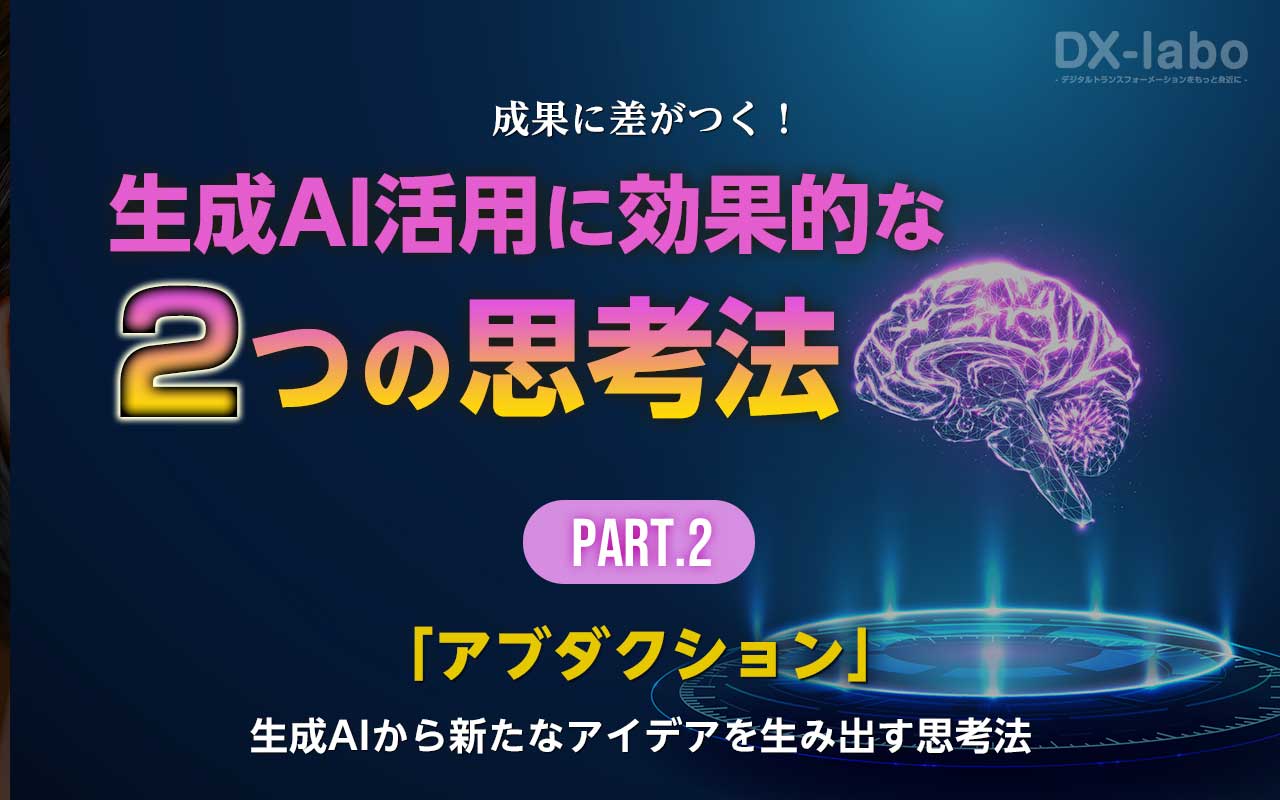
前半記事では、生成AIが出力する「もっともらしいウソ(ハルシネーション)」に振り回されないために有効な思考法「クリティカルシンキング」について解説しました。後半の今回は、生成AIを活用して創造的な価値を生み出す「アブダクション」という思考法を紹介します。
“未知の仮説”を生み出すアブダクション
アブダクションは、観察された事象やデータから、その原因を合理的に説明できる仮説(最もありえそうな仮説)を推測する思考法です。日本語では「仮説的推論」や「仮説形成」と訳されています。
元々アメリカの哲学者・論理学者・科学者C・S・パース(1839-1914)が提唱した推論方法のひとつであり、主に科学的探究において、観察だけでは導き出せない法則や因果関係を推測するために用いられてきました。
推論方法には他に「演繹法」と「帰納法」がありますが、それぞれの特徴を比較すると、アブダクションのユニークさがよくわかります。
・演繹法
例:「すべての人間は死ぬ→ソクラテスは人間→ゆえにソクラテスは死ぬ」
演繹法は一般的な原理・法則を前提に、個別の事象を導く推論方法です。論理的に確実な結論を導く一方で、前提にない仮説や発見を生み出すことはできません。
・帰納法
例:「このリンゴは赤い+あのリンゴも赤い→ゆえにすべてのリンゴは赤い(かもしれない)」
帰納法は複数の事象から共通点を見出し、そこから一般的な原理・法則を仮説として導く推論方法です。ただし、あくまで前提を一般化した仮説であり、また仮説である以上、必ずしも正しいとは限りません(例で言うと、別の色のリンゴが見つかった場合)。
・アブダクション
例:「地面が濡れている→雨が降ったのかもしれない」
先述の通り、観察された事象やデータから、直接観察できない原因を仮説として導く推論方法です。帰納法と同様、正しさは保証されませんが、知識や経験などをつなぎ合わせた直感的な思考の飛躍を伴うため、これまでにない仮説を生み出す可能性を秘めています。
こうした特徴から、アブダクションは「発見の論理」と呼ばれることもあります。その象徴的な例としてよく挙げられるのが、アイザック・ニュートンの「木からリンゴが落ちるのを見て万有引力の法則のヒントを得た」という有名なエピソードです。
生成AI時代にアブダクションが求められる理由
生成AI時代のビジネスにおいてアブダクションが重視される理由のひとつは、テキスト生成AI『ChatGPT』『Copilot』『Gemini』などの大規模言語モデル(LLM)が、演繹法と帰納法に基づく処理には一定の強みを持つ一方で、アブダクションに関してはまだまだ人間のほうが優れているという点にあります。
例えば、生成AIに「地面が濡れている理由は?」と尋ねると、上述の例と同じく「雨が降ったのかもしれない」という応答が返ってくる可能性はあります。しかしこれは、推論の結果ではなく、学習データに頻出する記述から次に続く言葉を統計的に選んでいるにすぎません。生成AIは仕組み上、データにない斬新かつ創造的な仮説を生み出すことが難しいのです。
もちろん、演繹法と帰納法もビジネスに不可欠であり、特に意思決定やデータ分析において重要な役割を果たします。しかし、業界を問わず「変革」が求められている現在、企業が喉から手が出るほど欲しいのは、「発見」や「イノベーション」につながる創造的なアイデアです。そして、それを生み出すことが一番の得意なのは、少なくとも現時点では人間という訳なのです。
アブダクション的思考を磨く“習慣”
冒頭で述べたように、本来アブダクションは科学的探究のために提唱された思考法であり、そのプロセスは非常に厳密です。しかし、いわゆる「アブダクション的」な思考は、実は多くのビジネスパーソンが日常的におこなっています。
例えばマーケティングでは、さまざまな顧客データをもとに、顧客自身も気付いていない潜在ニーズを仮説立てることが求められますが、こうした洞察はまさにアブダクション的な思考の一例です。そして、このようなスキルを磨くために有効な方法が、クリティカルシンキングと同様、日々の習慣付けです。
アブダクションの場合、特に意識したいのが「問いを立てる」習慣です。それも単に「なぜ?」と問うだけなく、ニュートンが「リンゴは地面に落ちるのに、なぜ月は落ちてこないのか」と対比して考えたと言われているように、事象やデータについて「○○は××なのに、なぜ□□は△△なのか?」「なぜ○○ではなく、□□なのか?」といった問いを立てるのも効果的です。
また、仮説立案力を向上させるには、常に複数の仮説を考え、それを検証可能な形に落とし込む習慣を持つことも大切です。なお、アブダクションについて理解を深めたい方は、やや専門的ながら、本記事でも参考にした『アブダクション-仮説と発見の論理』(米盛祐二著、勁草書房)という書籍が助けになります。
生成AIの効果=ユーザーのスキル
今回は、生成AI時代に求められるスキルとして思考力に焦点を当て、「クリティカルシンキング」と「アブダクション」という2つの思考法を紹介しました。
簡単にまとめるなら、クリティカルシンキングでAIの出力を吟味・検証し、そのうえでアブダクションによる仮説立案の起点や裏付けに活用することが、生成AIを価値創出につなげるための最も効果的なアプローチと言えるでしょう。
生成AIがビジネスや組織の変革を支える重要な技術であることは間違いありません。しかし現時点では、当初期待されていたような「万能ツール」ではありませんし、何よりその効果はユーザーのスキルによって大きく変わります。この点を忘れず、あくまで他のITツールと同じスタンスで付き合うことが、生成AIの可能性を最大限に引き出す鍵となるのかもしれません。